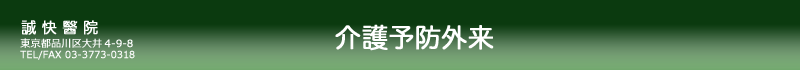−介護予防外来のご案内−
介護予防が切実な理由
2025年には昭和22年から24年に生まれの団塊世代が全員後期高齢者の仲間入りしました。
厚生労働省の統計によれば、80〜84歳の人が介護サービス必要とする割合は約25%、85〜89歳では約約47%と半数近くになります。
2024年現在約560万人の団塊世代が80歳を超えだすと、莫大な数の要介護人口が発生し、若年人口の減少と相まって介護サービス需給が逼迫します。
こうした危機的状態が顕在化するのが5年後からと推定され、医療・介護の2030年問題と心配されています。
「そうなるかもしれない」ではなく、ほぼ確実に起きてくる介護逼迫状態に行政はもちろん個人としても今から対策を立てないと、待っているのは介護難民の道です。
2014年の厚生労働省調査によれば、介護サービスの利用を開始すると居宅で12.3万円、施設で28.9万円の月額費用がかかるとされていました。物価高騰の影響もあり、現在では月額40万円の有料老人ホームも珍しくありません。
では、理想的な介護対策とは何でしょうか。
それは、言うまでもなく要介護にならず、自分のことは自分でできる自立の期間をぎりぎりまで長く維持することです。
言い換えれば、俗に言うPPK(ピンピンコロリ)をいかに実現するか、となります。
PPKを実現するための方法を知るには?
筆者も含め気づいたらなってしまった後期高齢者にとって、楽しくなさそうな要介護生活への突入を先延ばしすることは切実な目標です。
では、そうした介護予防を目指したとき、一体どこに行って誰に聞けば方法を教えてもらえるのでしょう。
生成AIで検索すると、地域包括支援センターなどが推奨されます。しかし、こうした施設は問題が起きてから対応方法を助言してくれる所であって、予防方法を教えてくれるわけではありません。
なぜこうしたすれ違いが起きるかというと、実は介護予防方法を研究・教育している施設や国家資格がないからなのです。
医師は病気については長い時間をかけて詳しく教育され、専門知識も豊富にあります。ですが、私が医学部に通っていた40年前も現在も医学教育のカリキュラムに介護予防の方法論は含まれていません。
もちろん薬剤師や柔道整復師、理学療法士、トレーナーの教育課程にもありません。
結局「切実なニーズはあるけれど受け皿がない」のが現実なのです。
誠快醫院の介護予防の取り組み
最近経営学でよく聞く言葉にパーパスがあります。
英語のパーパスを直訳すれば目的や目標となりますが、経営学では企業の存在意義や社会における価値を表す言葉です。
そして誠快醫院のパーパスは、恩師橋本敬三医師の医療/健康法則の操体理論をあらゆる場面で生かし、根本的に健康を回復・増進することです。
介護予防についても操体理論は非常に強力な方法論として応用できます。
操体理論で最も重要な法則に「後が気持ちいいは、体にいい」があります。
この法則を自分で調節可能な生活習慣項目である呼吸・飲食・運動・ストレス管理・環境調整に適応すれば、介護予防を含めた健康維持・増進が実現できるのです。
5つの生活習慣項目を各自の体質や環境に応じて調節・実行すると健康度が増し、病気や老化現象の予防につながります。
代表的な例を一つ挙げましょう。この方は、20年前にがんの再発予防目的で誠快醫院を受診されました。免疫増強効果のあるサプリメント/薬剤と生活習慣改善で再発は完全に抑制され、6年後には経過観察も修了となりました。
その後も軽度の高血圧の管理と健康維持を目的に当院通院を継続され、90歳の今も自立維持はもちろん、お嬢さんやお孫さんへの援助までされています。
原疾患の治癒のみならず90歳までの自立維持ができたのは、ご本人が大変真面目な性格で地道に生活習慣改善に取り組んできた成果だと確信しています。
もしこの記事の読者が真剣にPPKをめざしており、そのために一生使えるノウハウを求めているならば、誠快醫院の介護予防外来受診がきっとお役に立てます。
具体的な診療費は、最初の6回程度は二週間に一回の外来受診費がかかります。その後は、必要が生じたときのみの外来受診と、必須栄養補充のサプリメント代として月に2〜3万円程度の費用となります。それでも高額な介護サービスを受けて鬱々とした生活をするより、はるかに安上がりで充実した暮らしを送れるはずです。読者はどちらの道を選ばれますか?